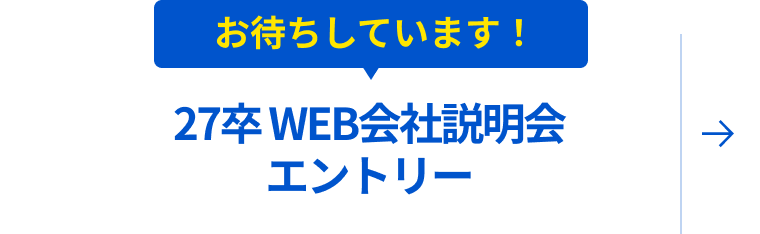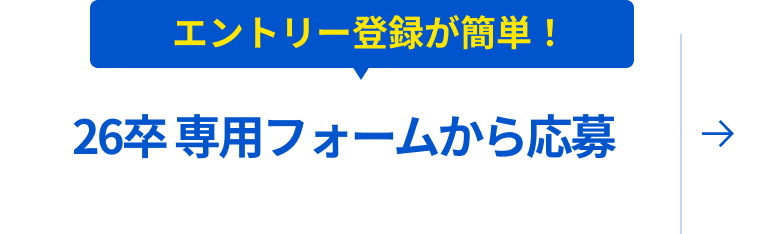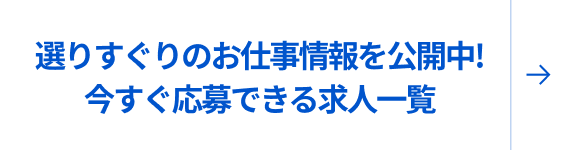ひたむきな姿勢で、テストから設計へ。

業務内容について船舶システムの動きを理解し、設計に挑む。
船舶関連のソフトウェア開発を担当しています。入社して半年ほどは、先輩方が作成したソフトウェアの単体テストをし、つくった製品が想定通りの動作を行うか確認していました。その後1年ほどは、コーディングを担当し先輩方が作成したソフトウェアを自分でも作るようになりました。
ソースコードの中身を十分に理解できるようになってからは、どうコーディングをしていくかを設計する役割に。設計を行う際には、クライアントからいただいた機能仕様書をもとに、システムの流れを可視化しています。

成長を実感したエピソードOK・NGの先にある原因解明。任されるエンジニアへの成長。
ソフトウェアの単体テストを行なっているとき、業務に慣れないうちは試験項目に対してOKやNGを報告するだけでしたが、徐々に仕事に慣れてきた頃には、実際にプログラムのソースコードをみて、なぜそのNGが起こるのかという原因調査を任せていただきました。
それは自分にとって非常に大きな一歩で、頑張ったことを評価されて、「次の仕事を任せてもらえた」という達成感と、自身がステップアップできているという高揚感にかられました。

新人時代の学びコードに残す一言が、未来の自分を助ける。
コーディングを担当するようになったころ、先輩から「コーディングする際にはグレーアウトして必ずコメントを残すこと」と言われ続けていました。当時はなぜそこまで口酸っぱく言うのか理解できていなかったのですが、しばらくして不具合が見つかったときに初めて理由がわかりました。
コメントを残すことによって、そのコードがどのような動きをするのか理解しやすく、不具合の原因がすぐに発覚するのです。コメントを残さないと、コードの動きから調査をすることになり、原因調査に時間がかかってしまいます。コメントの重要性を理解し、今ではコーディングする際に必ずコメントを付けるように心がけています。

就活中の方へメッセージ
就活で大事なことは自分に嘘をつかないこと。 妥協せず、本当にやりたいことを軸にすることで、納得のいく結果を得られるはずです。頑張ってください!
他のインタビューを見る
-
新卒採用エントリーNEW GRADUATE
-
キャリア採用エントリーCAREER RECRUITMENT